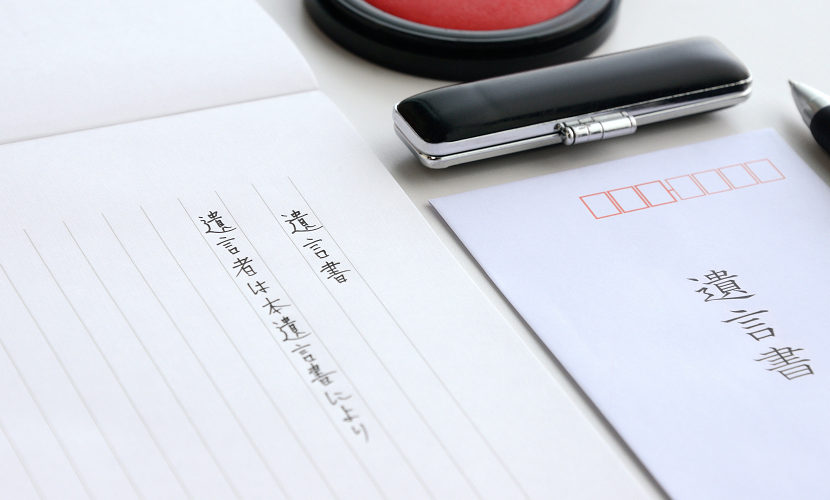遺言書を作成するメリット・デメリットと注意点
終活をしている、遺産相続について適切な処理をしておきたい、などの理由で「遺言書」を作成しておこうと思っている方も多いのではないでしょうか?
遺言書を作成しておくメリットとデメリットについてお伝えした上で、遺言書作成の際の注意点をお伝えします。
遺言書作成・相談サービスの対応地域
埼玉県
遺言書作成・相談サービスのお問い合わせ
遺言書作成・相談サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
遺言に関するご相談は、無料です。
埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
遺言書って何でしょうか
まず、遺言書とはどのようなものなのでしょうか。
イメージだけなら、家族への思いや自分の財産について誰に譲る…などの事を書いてる書面で、死んだら弁護士が読み上げる…というものではないでしょうか。
定義をするならば遺言書とは「遺言を書面にしたもの」を言います。
そして遺言とは、民法に規定がされている、自分の財産等に関する最後の意思表示をしたものです。
法律の規定では例外的に書面になっていなくても遺言の効果が認めれるものもあるのですが、現実に用いられる遺言は書面を作成して有効になるものがほとんどなので、基本的には遺言は書面になっていると考えましょう。
相続人となる家族などに感謝の言葉を遺言書の中で述べたりすることはできますが、あまり一般的ではなく、財産処分に関するもの以外については遺書などの手紙やエンディングノートといわれるものでされるのが一般的です。
2.遺言書を作成しておくことのメリット
では遺言書を作成しておくことにどのようなメリットがあるのでしょうか。
2-1.相続争いが起きにくい
遺言をせずに相続が開始すると、法律の規定にのっとった相続が開始されます。
この場合、調整の規定はありますが、同居している相続人・後を継ぐ相続人・あまり交流の無い相続人、すべて一律の相続分が適用されます。
その人たちが、相続分に基づいて協議をして遺産分割をするため、不公平感が生じたり、場合によっては相続人相互間で裁判に発展して家族の絆が壊れてしまう、という事にもなりかねません。
遺言書を作成して遺言を遺しておくと、遺留分という規定に基づく一定の制限はありますが、相続に関する指定をできます。
つまり、相続人としては被相続人の死後に協議をする必要などがなくなるため、スムーズに遺産相続ができるようになり、争いの芽を摘むことができるようになります。
2-2. 相続人以外の人にも財産を残してあげることができる
遺言を残さないで相続が開始すると、法定相続人という基本的には親族関係にある人に対してのみ財産が承継されることになります。
しかし、遺言書では相続人以外の方にも死後に財産を譲り渡すことが可能です。
生前お世話になった、長男のお嫁さんや、お手伝いさんなどに財産を譲り渡すような事も可能ですし、孫に財産を遺言で譲り渡すことで相続税対策をすることができるなどのメリットがあります。
3.遺言書作成にもデメリットはある?
そんな遺言書作成ですが、デメリットもあります。
3-1.手続きの負担
まず、遺言書を作成する手続きにはそれなりの負担が伴います。
遺言書は民法の規定に従った厳格なものでなければなりません。
一番よく利用される公正証書遺言では、公証人・交渉役場とのやり取りをして費用をかけて行います(通常は弁護士などの専門家を利用しながら作成しますので、専門家への報酬もかかります)。
また次に利用される、自筆証書遺言で遺言書を作成する場合には、現状全文を手書きで書く必要があり、間違った場合には◯字削除・◯字加入など、厳格な修正方法があり、間違うと遺言書がまるごと無効になるというリスクを背負います。
これらの遺言書を一度作成すると、訂正するためには訂正のための遺言書を作成する必要があります。
これらの正確な手続きを踏む負担があります。
3-2.遺言をしたという事実が外に出るのは場合によってはデメリット
遺言書の作成については、たとえば公正証書遺言や秘密証書遺言というものを利用した場合には、証人という人を用意しなければなりません。
そのため家族に内緒で作成したとして、遺言書を作成した事実を知られてしまうと、どのような遺言をしたのか?ということが争いの火種になるようなこともあります。
これに関しては、家族で話し合った上で遺言をしたり、話し合うのが難しい状況である場合には弁護士や行政書士など、法律上秘密を守る義務(守秘義務)を負っている人たちに依頼をすると、証人となった内容も秘密にしてくれます。
4.遺言書を作るときの注意点
遺言書を作るときにはどのような注意点があるのでしょうか。
遺言書をつくる際には、できる限り法律の専門家に依頼するべきといえます。
これは、上述したとおり遺言に関しては民法が厳格に規定しており、違反すると遺言書が無効になってしまうことがあります。
遺言書自体が無効になるケースとしては自筆証書遺言をする場合ですが、公正証書遺言をする場合でも遺留分の規定に反してしまうなどの恐れがあったり、手続きをするにあたって公証人という元裁判官とやりとりをしなければならないのは負担です。
確かに費用はかかるものですが、手続きを確実かつスムーズにすすめるためには、弁護士・税理士・司法書士・行政書士などの法律専門家に相談しながらすすめましょう。
遺言書の種類
遺言書には、3つの種類があり、それぞれ決められた様式があります。
遺言書は様式の条件を満たしていることが、まず重要になります。
[su_box title="3つの遺言書" style="soft" box_color="#f34cea"]
[su_service title="自筆証書遺言" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"]遺言者が、遺言の全文(別紙の財産目録を除く。)・日付・氏名を自書し、捺印した遺言 [/su_service]
[su_service title="公正証書遺言" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"]遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人および2人以上の証人が、内容を承認の上署名・捺印した遺言 [/su_service]
[su_service title="秘密証書遺言" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"]遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言 [/su_service]
[/su_box]
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文(目録を含むすべて)を手書きし、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です(すべてを自書しないとだめで、パソコンやタイプライターによるものは無効です。
※ただし,平成31年1月13日から,民法改正によりパソコン等で作成した目録を添付したり,銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を目録として添付することが認められるようになります。)。
自筆証書遺言は、内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合には、法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり、後に紛争の種を残したり、無効になってしまう場合もあります。誤りを訂正した場合には、訂正した箇所に押印をし、さらに、どこをどのように訂正したかということを付記して、そこにも署名しなければならないなど方式が厳格なので、方式不備で無効になってしまう危険もつきまといます。
また、自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、必ず、家庭裁判所にこれを持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければなりません。自筆証書遺言は、これを発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえません。
また、自筆証書遺言は全文自書しないといけないので、当然のことながら、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方は、利用することができません。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
公正証書遺言は、複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にできますので、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。
また、公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
また、自筆証書遺言は、全文自分で自書しなければなりませんので、体力が弱ってきたり、病気等のため自書が困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできませんが、公証人に依頼すれば、このような場合でも、遺言をすることができます。署名することさえできなくなった場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
なお、遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較すると、メリットが多く、安全確実な方法であるといってよいと思われますが、遺言者にとっては、費用のかかることが難点と言えるでしょう。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり、自書である必要はないので、ワープロ等を用いても、第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で、これを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。
その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ、遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができますが、公証人等は、その遺言書の内容を確認することはできませんので、遺言書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、無効となってしまう危険性がないとはいえません。
また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように、この遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て、検認手続を受けなければなりません。
遺言事項
遺言事項とは遺言に書いた項目のうち法的な効力を発揮するもののことを言います。
財産に関する遺言事項
- 相続分や遺産分割方法の指定
- 遺贈
- 寄付や一般財団法人の設立
- 信託の設定
を遺言で定めることができます。
相続分や遺産分割方法の指定
法定相続人の遺産相続については民法で法定相続分が決まっています。しかし、法定相続分の規定は自由な遺産分割妨げない任意規定です。
相続人が納得いくように遺産を分割することも、遺言によって遺産分割を指定することも可能です。遺言は相続分だけを定めて自由に遺産を分けてもらう方法と相続人ごとに受け継ぐ財産を指定する方法のどちらも定められます。
相続分は自分で定める以外に、第三者に定めさせることも可能です。
遺産分割では特別受益が問題となります。特別受益とは生前に他の相続人に比べて格別に受けた恩恵のことで、遺産分割の際は受け取った財産の持ち戻しを他の相続人が要求できます。遺言書は特別受益の持ち戻しを免除することができます。
遺産分割の禁止の遺言は、5年間遺産分割の禁止を遺言することができます。
遺贈
遺贈とは、遺言によって法定相続人ではない誰かに財産を引き継ぐことです。遺言は、法定相続人以外の人を相続人にする効力を持っていないため、相続でなく遺贈という形になります。
遺留分の請求
法定相続人の相続をする権利を無視して、第三者にすべての財産を遺贈することはできません。遺言によって第三者に遺産の全部が遺贈される場合であっても、相続人は民法に定められた遺留分を請求する権利が認められています。
寄附や一般財団法人の設立
遺産を寄付することや、自らの意思で財団法人を立ち上げることが可能です。財団法人とは財産そのものに法人格を与え、その運用が主な業務となります。財団法人の設立は節税対策にも効果的です。
信託の設定
財産の信託について遺言で決めることができます。信託する財産や信託銀行の指定をすることができます。
身分に関する遺言事項
- 子供の認知
- 未成年後見人の指定
- 推定相続人の廃除
を遺言することができます。
子供の認知
子供の認知は遺言によって行うことができます。子どもを認知すると遺産相続において嫡出子と同じ扱いになりますので、嫡出子の法定相続分や兄弟姉妹の相続する権利に大きく関わります。
未成年後見人の指定
未成年後見人や未成年後見監督人の指定も遺言で行えます。自分が亡くなった後に残される小さな子供が安全に過ごすための未成年後見人の指定です。
相続人の廃除とその取消し
遺言では、推定相続人の廃除をすることができます。例えば、虐待があった場合、財産を勝手に浪費した場合などはそれを理由に相続人の廃除ができます。
相続人の廃除はよほどの事情がないと行えず、できれば遺言で指定するより、生前に相続人廃除の申し立てをすることが望ましいと言えます。
また、すでに廃除した推定相続人をもう一度相続できるようにする推定相続人廃除の取り消しも遺言によってすることができます。
廃除できる相続人は、配偶者、子、直系尊属に限られていて、兄弟は遺留分を認められていないため、廃除もすることはできません。
遺言執行に関する遺言事項
遺言執行者の指定
遺言執行者の指定とは、遺言の内容を実現するための人です。子供の認知や他人への特定遺贈、推定相続人の廃除などは遺言執行者が必要なので、事前に選んでおくことが望ましいと言えます。
遺言執行者は信頼のおける第三者が望ましく、実務に慣れている専門家などが適任です。遺言書を遺言執行者に預けておくことや公正証書遺言として公証役場に保管してもらうことがおすすめです。特に公正証書遺言は検認の必要がないため手続きが楽になります。
もし、遺言執行者を定めない場合は家庭裁判所が選任を行います。遺言執行者を定めないだけで手続きが増えます。遺言執行者が拒否した場合や死亡した場合も家庭裁判所が選任することとなります。
その他の遺言事項
- 祭祀継承者の指定
- 生命保険受取人の指定
祭祀継承者の指定
仏壇やお墓などを相続する人を遺言によって決めることができます。遺言によって定めない場合は、地域の慣習で決め、慣習が認められない場合は家庭裁判所によって定めます。
生命保険受取人の指定
生命保険受取人の指定や変更が可能です。生命保険は被相続人の死亡によって受け取る財産なので、厳密には相続財産ではありません。このような財産のことをみなし相続財産と言います。遺言によって生命保険受取人を指定できるのは被相続人自らが保険料負担者となっている場合です。
同じくみなし相続財産である死亡退職金については遺言の内容で受取人や分け方を決められず、労働基準法施行規則に従います。
農地の相続人以外の方への遺贈と農地法3条許可
相続人に対して農地を遺贈する場合は、包括遺贈(財産内容を指定せず割合のみを指定して遺贈)でも特定遺贈(特定財産を特定人に対して遺贈)でも農地法3条の許可は不要です。
相続人以外の方に対して、農地を含む財産を包括遺贈する場合は農地法3条の許可は不要です。
相続人以外の方に対する特定遺贈の場合は、農地法3条の許可が必要となります。
遺言書関連情報
自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日施行)と保管制度の創設(令和2年7月10日施行)
風俗営業者の相続承認方法(60日以内)。遺言書での営業継続否認
遺言書相談|相続人一人に全財産を相続させる遺言書。自分の分は?
公正証書遺言・秘密証書遺言の証人2名
公正証書遺言・秘密証書遺言を作成する場合、証人2名が必要ですが、当事務所では、2名の証人の引き受けも行っております。
遺言に係るよくある質問
[su_service title="遺言書でお墓を守る人を指定することはできますか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5bef5a"]できます。ただし、指定された人には、負担がかかるので、財産を余分に与えるなど考慮してあげると 良いかと思います。[/su_service]
[su_service title="遺言で相続分(相続人が遺産を受ける割合)を指定することはできますか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5bef5a"]できます。ただし、遺留分に注意し、相続人の公平感にも配慮すると良いでしょう。[/su_service]
[su_service title="遺言書の中に家族へメッセージを残すことはできますか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5bef5a"]「付言事項」という形で入れることができます。
付言事項とは、法的な効力はありませんが、遺言書の最後に書き加えることができる文章です。[/su_service]
[su_service title="お世話になったヘルパーさんに遺産を分けられますか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5bef5a"]遺言書で、ヘルパーさんに遺贈をすることができますが、相続人の遺留分を侵害する場合には、相続人からの 遺留分の主張がある場合があります。 [/su_service]
[su_service title="遺言書でペットに遺産を分けられますか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5bef5a"]ペットに遺産を残したときは、「負担付遺贈」、「財団の設立」、「遺言書信託」など間接的な形で ペットのために遺産を使うようにしてもらう方法があります。※「ペット信託」という方法もあります。 [/su_service]
[su_service title="遺言書を書いたあとで、相続人が遺言者より先に亡くなった場合は、どうなりますか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5bef5a"]相続人が遺言者より先に亡くなった場合は、その相続人が受け取ることになっていた財産は、遺言書を 書き直さない限り、法定相続人の間で改めて、分割協議をしなければなりません。そのようなことを 防ぐために、遺言書の中であらかじめ別の人を定めておくことができます。(予備的遺言) [/su_service]
法定相続分と異なる遺言を残すときは
法定相続分と異なる遺言を残すときは、その遺言書に従って、手続きをしてもらう「遺言執行者」を 決めて、遺言書に残した方が良いでしょう。
遺言執行者とは
遺言者は、自分が死亡したあとに遺言が正しく実行されるのを見届けることができません。
遺言者は、責任をもって遺言を実行する人「遺言執行者」を遺言書の中で指定することができます。
遺言執行者は、遺言を執行するために必要なことができ、相続人は遺言の執行を妨げることができないよう民法に定められています。
遺言執行者が指定されていなかった場合は、家庭裁判所に、相続人と利害関係のない遺言執行者を選任をしてもらうことはできます。
ただ、遺言執行者は、必ず選任しなければならないものではありません。
当事務所では、遺言執行者の受任も行っております。